スーパーカブ50のカスタムパーツを探しているけれど、種類が多すぎてどこから手をつければ良いか迷っていませんか。
定番のマフラーやシートの交換から、ホイールやレッグシールドの変更、さらにはオフロードスタイルへの挑戦や、角目モデル、プロカスタムといった特定の仕様に合わせたパーツ選びまで、選択肢は非常に多彩です。
バッテリーのような消耗品の交換もカスタムの第一歩と考えられます。
この記事では、スーパーカブ50 カスタムパーツの選び方から、カスタムパーツおすすめ人気10選まで、幅広く紹介していきます。
- スーパーカブ50の代表的なカスタムパーツの種類と特徴
- 定番カスタムパーツの人気トレンドと選び方の基本
- オフロードや角目モデルなど特定のスタイルに合わせたパーツ
- バッテリー交換などメンテナンスに必要なパーツの知識
スーパーカブ50:カスタムパーツの選び方

- カスタムパーツおすすめ人気10選
- 定番のマフラー交換で音と走りを楽しむ
- シート交換で見た目と乗り心地を改善
- 個性を出すレッグシールドの交換
- ホイールカスタムで足回りを強化
カスタムパーツおすすめ人気10選
スーパーカブ50のカスタムは、国内外の多くのメーカーからパーツが供給されており、その圧倒的な豊富さが魅力です。ここでは、特に人気が高く、多くのオーナーがカスタムの第一歩として選ぶ代表的なパーツを10種類紹介します。これらは、見た目を大きく変えるものから、走行性能や快適性を向上させるものまで、様々なニーズに応えるものです。
1. マフラー
交換による変化を最も体感しやすいパーツがマフラーです。メリットは、排気音の変化、デザイン性の向上、そして軽量化にあります。音質は、重低音を響かせるメガホンタイプ、歯切れの良いサウンドのキャブトンタイプ、元気な音質のアップタイプなど様々です。デザインも車体の印象を決定づける重要な要素となります。
一方で、注意点もあります。多くの社外マフラーは「抜け」が良くなるため、高回転域での伸びが良くなる代わりに、発進時などの低速トルクが純正より細く感じられる場合があります。また、公道で使用するには、排気音量や排出ガス規制をクリアした「政府認証(JMCA認証など)」品を選ぶ必要があります。認証のないマフラーは整備不良となるため注意が求められます。
2. シート
ライダーが常に触れ、目にするシートもカスタム満足度が非常に高いパーツです。最大のメリットは、デザイン性と快適性の変更が可能な点です。表面に縦じま模様を施した「タックロール」や、ひし形模様の「ダイヤステッチ」はクラシカルな雰囲気を高めます。
機能面では、シート内部のウレタン(あんこ)を薄くした「ローダウンシート」で足つき性を改善したり、逆にクッション性を高めたシートで長距離走行の疲労を軽減したりできます。また、原付二種登録を前提とした「ダブルシート」や「ピリオンシート(タンデム用)」も人気です。
ただし、デザイン優先の薄型シートは、長時間の運転でお尻が痛くなりやすいというデメリットも存在します。また、製品によっては縫い目からの浸水に弱い場合もあるため、雨天時の使用も考慮して選ぶと良いでしょう。
3. リアキャリア
スーパーカブの実用性を象徴するリアキャリアも、用途に応じて交換が推奨されるパーツです。純正キャリアを、より面積の広い大型キャリア(プロモデル用など)に交換すれば、大きなリアボックスやキャンプ道具の積載性が大幅に向上します。
逆に、荷物をほとんど積まない場合は、小さく薄い「フラットキャリア」に変更することで、リア周りをスッキリとスタイリッシュに見せるカスタムも人気があります。
選ぶ際の注意点として、キャリアごとに「最大積載重量」が定められているため、用途に合った耐荷重の製品を選ぶことが大切です。また、取り付け穴の位置がモデルや年式によって異なる場合があるため、適合確認は必須です。
4. ボアアップキット
エンジンの根本的な走行性能を引き上げるカスタムが、ボアアップキットの導入です。これは、エンジンのシリンダーとピストンを交換し、排気量を50cc以上(例:75cc、88cc、110ccなど)に増大させるものです。最大のメリットは、交通の流れに乗りやすくなる力強い加速や、坂道を楽に登れる登坂能力の向上です。
しかし、これは最も注意が必要なカスタムでもあります。排気量が50ccを超えると原付一種ではなくなるため、必ず管轄の役所にて「原付二種登録」(ピンクナンバーなど)への変更手続きが法的に義務付けられています。
さらに、運転には「小型限定普通二輪免許(AT限定も可)」以上が必要となります。登録変更に伴い、加入している自賠責保険や任意保険(特にファミリーバイク特約)の適用範囲についても、保険会社への確認が必須です。また、エンジンに負荷がかかるため、オイル管理の重要性が増すほか、車種やキットによっては耐久性や燃費が低下する可能性も考慮する必要があります。
5. サスペンション
乗り心地や走行安定性に直結するのがサスペンションです。カスタムとしては、主にリアショックアブソーバーの交換が一般的です。純正よりも性能の高い社外品(YSS製や東京堂製など)に交換することで、路面からの衝撃吸収性が向上し、長距離走行での疲労軽減やコーナリング中の安定感アップが期待できます。
また、ローダウン(車高を下げる)目的で、純正より短いショートサスペンションを選ぶことも可能です。ただし、極端に車高を下げると、路面の大きなギャップで車体が底付きしやすくなったり、乗り心地が硬くなったりするデメリットも生じます。
フロントに関しては、カブ特有のボトムリンク式サスペンションの動きを制御する「強化フロントショック」や「サブダンパーキット」なども販売されています。
6. レッグシールド
スーパーカブの象徴とも言えるレッグシールドは、スタイル変更の効果が非常に大きいパーツです。純正のホワイトやベージュから、ブラックや他色に変更するだけで、車体のイメージは一新されます。
素材も純正の柔らかいPE樹脂だけでなく、光沢のあるABS樹脂製や、塗装に適したFRP製などがあります。また、純正よりも幅を狭くした「ナロータイプ」に交換すれば、エンジン周りが強調され、軽快なストリートスタイルを演出できます。
注意点としては、社外品、特に安価な製品では、車体に取り付けるネジ穴の位置が微妙にずれている「フィッティング」の問題が発生することがあります。また、前述の通り、ナロータイプはデザイン性と引き換えに、本来の優れた防風・防汚性能が低下する点も理解しておきましょう。
7. タイヤ
タイヤは走行性能を支える消耗品であると同時に、見た目の印象を大きく左右するカスタムパーツです。用途に合わせて様々な種類が選べます。例えば、クラシカルな雰囲気を高める「ビンテージパターンタイヤ」、雨天時のグリップやコーナリング性能を重視した「ハイグリップタイヤ」、そして林道なども楽しみたい場合の「ブロックタイヤ」などです。
選ぶ際には、純正のリム幅に適合するサイズを選ぶことが基本です。太いタイヤを履かせたい場合は、フェンダーやスイングアームとの干渉リスクがないかを確認する必要があります。また、スーパーカブのスポークホイールはチューブタイヤが基本となるため、タイヤ交換時にはタイヤチューブやリムバンドの状態も確認し、必要に応じて同時交換することが推奨されます。
8. ハンドル周り(グリップ・ミラー)
比較的安価かつ手軽に交換でき、常に視界に入るため満足度の高いカスタムがハンドル周りのパーツです。グリップは、握り心地やデザイン(クラシカルな樽型、スポーティーな細身タイプなど)で選べます。素材もゴム製、アルミとゴムの複合タイプなど多彩です。
ただし、注意点として、丸目のスーパーカブ(角目カスタムを除く)のハンドル径は19mmという特殊なサイズが多いため、一般的な22.2mm用のグリップは適合しません。必ず「カブ用」や「19mm対応」と記載された製品を選ぶ必要があります。
ミラーも、純正の四角いデザインから、円形や楕円形のスタイリッシュなものに交換するのが人気です。ただし、保安基準で定められた鏡面の面積や形状を満たしていないと、整備不良となる可能性があるため注意しましょう。
9. ライト類(LED・フォグランプ)
年式の古いスーパーカブ50は、純正ヘッドライトが暗く、夜間走行に不安を感じることがあります。このような場合、ヘッドライトバルブを高輝度な「LEDバルブ」に交換するキットが人気です。夜間の視認性が劇的に向上し、安全性アップに直結します。また、LEDは消費電力が少ないため、バッテリーへの負担を軽減できるメリットもあります。
ただし、古い年式のカブは発電が交流(AC)の場合があり、直流(DC)専用のLEDバルブはそのままでは使えません。必ず「交流対応」の製品を選ぶか、配線を加工して直流化する必要があります。
さらに、補助灯として「フォグランプ」を追加するカスタムも有効です。取り付け位置や明るさには保安基準の定めがあるため、確認が必要です。
10. ステップ・ペダル類
足元の操作性とドレスアップを両立させるのが、ステップやペダル類のカスタムです。純正のゴム製ステップを、アルミ削り出しのスタイリッシュなステップに変更するだけで、足元の印象が引き締まります。また、オフロード走行を考慮し、踏み面積が広く滑りにくい「ワイドステップ」も人気があります。
シフトペダルも、純正の「シーソーペダル」(前側でシフトダウン、後側でシフトアップ)の操作感を変更するため、一般的なバイクと同じ「リターン式ペダル」に変更するキットがあります。これは好みによりますが、操作性を統一したい場合に選ばれます。
これらのパーツは、キタコ、SP武川、アウトスタンディング、YSS、デイトナ、旭風防など、数多くの専門メーカーから販売されています。自分の好みや予算、目指すスタイルに応じて最適なパーツを選ぶ楽しみこそが、スーパーカブカスタムの醍醐味と言えるでしょう。ただし、カスタムを行う際は、必ず自分の車両の年式やモデルに適合するかを確認し、安全基準を守って楽しむことが最も大切です。
定番のマフラー交換で音と走りを楽しむ

マフラー交換は、スーパーカブ50のカスタムにおいて、その効果が視覚と聴覚の両方で最も分かりやすい、非常に人気の高いカスタムの一つです。純正マフラーは静粛性や耐久性に優れていますが、社外品に交換することで多くの魅力的な変化を得られます。
主なメリットは、排気音の変化です。純正の静かな音から、重低音が心地よく響くタイプや、単気筒エンジンらしい歯切れの良いパルス感が強調されるタイプなど、マフラーの種類によって様々なサウンドプロファイルを楽しめます。次に、デザイン性の向上も大きな要素です。車体全体のイメージを左右するため、選ぶマフラーによってバイクの方向性が決まると言っても過言ではありません。
また、素材の変更による軽量化も期待できます。純正のスチール製マフラーに対し、社外品で一般的なステンレス製や、さらに高価なチタン製のものを選べば、車体重量の軽減に貢献し、取り回しや運動性能の向上にもつながります。
主なマフラーの種類と特徴
| マフラータイプ | 見た目の特徴 | 音質の傾向 | メリット・デメリット |
| キャブトンタイプ | 魚の尾びれのような後端部。 クラシカル。 | 歯切れが良く、やや大きめ。 | メリット: クラシカルなスタイルに最適。 デメリット: 抜けが良すぎると低速トルクが細る場合がある。 |
| メガホンタイプ | サイレンサーが後方に向かって広がる形状。 | 重低音が効き、太い音質。 | メリット: スポーティーかつレトロな印象。 デメリット: 製品により音量が大きめなものがある。 |
| ダウンマフラー | 純正に近い、車体下部を通る取り回し。 | 製品により様々。 比較的ジェントルなものが多い。 | メリット: スタンダードなスタイルを崩さない。 センタースタンドが使える製品が多い。 デメリット: 大きな個性は出しにくい。 |
| アップマフラー | エキパイが上向きに取り回され、サイレンサーが高い位置にある。 | 歯切れが良く、元気な音質のものが多い。 | メリット: オフロードスタイルやアクティブな印象に最適。 障害物に強い。 デメリット: センタースタンドが使えなくなる製品が多い。 乗降時に足が触れやすい。 |
一方で、マフラー交換にはいくつかの注意点が存在します。最も重要なのは、公道走行の可否です。排気音量や排出ガス規制をクリアした証である「政府認証(JMCA認証など)」プレートが付いていないマフラーは、違法改造とみなされ、整備不良として取り締まりの対象となる可能性があります。必ず認証済みの製品を選んでください。
また、マフラーの構造によっては、純正で最適化されていたエンジン特性が変化することがあります。特に抜けの良いマフラーに交換した場合、高回転域でのパワーは向上するものの、発進時や低速走行時に重要となる低速トルクが若干低下する傾向があります。この特性変化を理解した上で、自分の走行スタイルに合った製品を選ぶことが求められます。
シート交換で見た目と乗り心地を改善

シート交換も、マフラーと並んでカスタムの満足度が非常に高い定番メニューです。シートは車体デザインの中でも大きな面積を占めるため、ここを変更するだけでバイクの雰囲気が一新されます。同時に、ライダーの体重を支え、操作性に直結する部分でもあるため、機能面での変化も大きいのが特徴です。
最大のメリットは、やはりデザイン性の向上です。純正のシンプルなシングルシートから、表面に縦じま模様が施された「タックロールシート」や、ひし形模様の「ダイヤステッチシート」に変更するだけで、一気にクラシカルでおしゃれな雰囲気を演出できます。フラットな形状のシートを選べば、カフェレーサー風のスタイルにも近づけられます。
機能面でのメリットも見逃せません。例えば、シート内部のウレタン(通称:あんこ)の量を調整してシート高を下げた「ローダウンシート」は、足つき性が格段に向上します。これにより、信号待ちなどで両足がしっかりと地面に着くようになり、小柄な方でも安心して運転できるようになります。逆に、長距離ツーリングを主眼に置く場合は、クッション性に優れたウレタンを使用したシートを選ぶことで、お尻の痛みを軽減し、長時間の運転でも疲れにくくする効果が期待できます。
また、実用性を高める選択肢として「ダブルシート(ロングシート)」や、純正キャリア上に追加する「ピリオンシート(タンデムシート)」もあります。これらを取り付けることで二人乗りが可能になりますが、50ccのままでは法規上二人乗りはできません。必ずボアアップによる原付二種登録を行った上で使用する必要があります。
ただし、社外品シートを選ぶ際にはいくつかの留意点があります。特にローダウンシートは、足つき性を優先するあまりクッション性が極端に低い製品も存在します。デザインは良くても、短時間の走行ですぐにお尻が痛くなる可能性もあるため、レビューなどを参考に乗り心地も考慮することが大切です。
さらに、製品によってはシート表皮の防水処理が不十分で、雨天走行後や洗車時に縫い目から水が染み込み、ウレタンが水を含んでしまうケースも報告されています。雨天時も乗る場合は、防水性を謳った製品を選ぶか、駐車時にシートカバーをかけるなどの対策を講じると良いでしょう。取り付けに関しても、年式やモデル(スタンダード、角目カスタム、プロなど)によってシートベースの形状やヒンジ(蝶番)の位置が異なるため、購入前に自分の車両に間違いなく適合するかを厳密に確認することが求められます。
個性を出すレッグシールドの交換
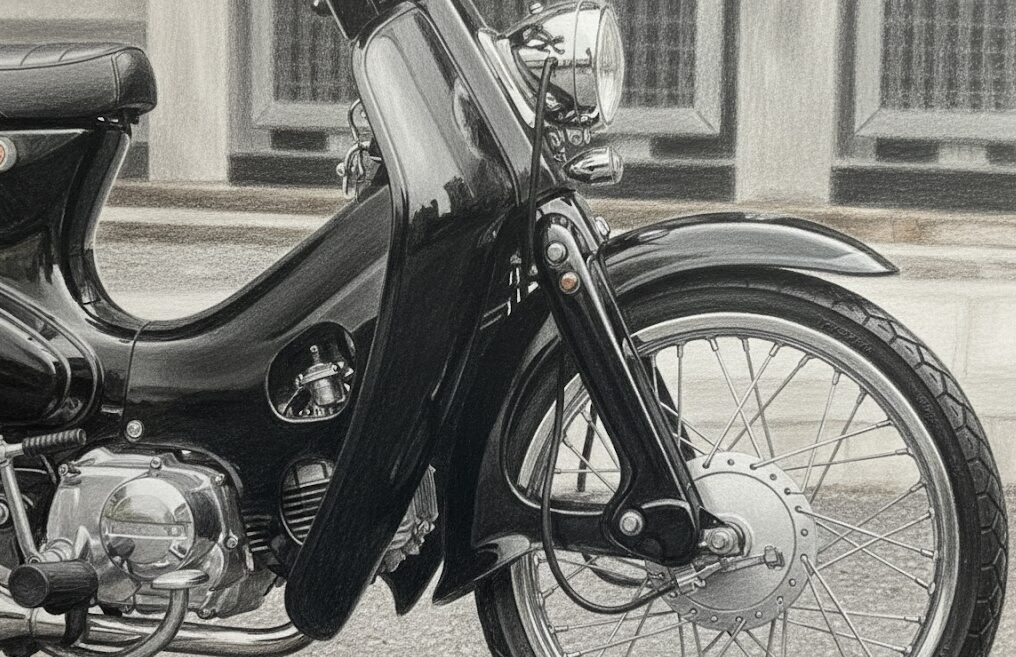
スーパーカブの最大のアイコンとも言える白いレッグシールドは、走行中の風や雨、泥はねからライダーの足元を守る、非常に機能的なパーツです。この象徴的なパーツをあえて交換することで、ノーマルとは一線を画す個性的なスタイリングを生み出すことができます。
レッグシールド交換の最大のメリットは、車体イメージの大幅な変更(イメチェン)が可能な点です。純正のPE樹脂(ポリエチレン)製、色はホワイトやベージュが基本ですが、社外品には様々な選択肢があります。例えば、純正カラーにはないブラックのレッグシールドに交換するだけで、車体全体が引き締まり、精悍な印象に一変します。素材も、純正の柔らかい質感とは異なる、硬質で光沢のあるABS樹脂製や、塗装のベースにも適したFRP(繊維強化プラスチック)製のものがあります。FRP製を選べば、車体色と同じ色に塗装して統一感を出すといった、より高度なカスタムも可能になります。
形状の変更も大きなポイントです。純正よりも幅を大幅に狭く(スリムに)した「ナロータイプ」のレッグシールドは、エンジン周りの露出が増え、軽快でスポーティーな「チョッパー」スタイルや「ストリート」スタイルのカスタムによく用いられます。
一方で、注意点も存在します。最も多いトラブルは、社外品、特に安価な製品における精度の問題です。素材が極端に薄かったり、成形が甘かったりするほか、車体に取り付けるためのネジ穴の位置が微妙にずれており、そのままでは装着できず、穴を広げたりステーを曲げたりといった加工が必要となる場合があります。
また、デザインを優先してナロータイプなどに変更した場合、トレードオフとして純正が持っていた高い防風性能や防汚性能が低下することは避けられません。特に雨天時や冬場の走行では、足元に当たる風や水の量が増えることを覚悟しておく必要があります。とはいえ、比較的大きな面積を占めるパーツであるため、交換によるドレスアップ効果は非常に高く、手軽に個性を追求したい場合には有効なカスタム手法です。
ホイールカスタムで足回りを強化

足回りの印象を決定づけ、走行性能にも影響を与えるのがホイールカスタムです。スーパーカブ50の純正ホイールは、スタンダードモデルで前後17インチ、プロモデルでは前後14インチの、クラシカルなスポークホイールが採用されています。
カスタムの方向性として最も一般的なのは、リムの交換です。純正のリムはスチール(鉄)製ですが、これをアルミ製のリムに交換するカスタムが人気です。アルミリムはスチールに比べて大幅に軽量であるため、いわゆる「バネ下重量」の軽減に直結します。バネ下重量が軽くなると、サスペンションの動きが良くなり、路面追従性が向上するほか、ハンドリングがより軽快になる効果が期待できます。
また、見た目のインパクトを重視するカスタムとして、純正よりも幅の広い「ワイドリム(太リム)」への交換も定番です。例えば、純正が1.2J幅のところを1.85Jや2.15Jといった太いリムに変更し、それに合わせてタイヤも太いサイズを装着します。これにより、リアビューに迫力が生まれ、安定感のあるどっしりとしたスタイルを構築できます。ただし、ワイド化する際には、太くなったタイヤやチェーンがスイングアームやチェーンカバーに干渉しないか、チェーンライン(前後のスプロケットを結ぶ直線)がずれないかなど、慎重なサイズ選びと調整が求められます。
さらに、スタンダードな17インチモデルをベースに、リトルカブ用の14インチホイールを移植し、意図的に小径化(インチダウン)するカスタムも存在します。「リトルカブ化」とも呼ばれ、車高が下がり、タイヤのハイト(厚み)と相まって、ロー&ファットなコンパクトスタイルを実現できます。この場合、ホイールだけでなく、14インチ化に伴うフロントフェンダーの位置調整や、速度表示を正確にするためのメーターギアの交換といった作業も必要になります。
近年では、スポークホイールではなく、メンテナンス性に優れる(スポークの錆びや緩みの心配がない)キャストホイールを装着するカスタムも見られます。これらのカスタムは、ブレーキ周り(ドラムブレーキのハブごと交換、あるいはディスクブレーキ化)の移植や調整も伴うため、難易度は上がりますが、足回りの印象を根本から変えることが可能です。
特色あるスーパーカブ50:カスタムパーツ

- オフロード仕様にするカスタム
- 角目モデルのカスタムポイント
- プロ カスタムの活用法とパーツ
- メンテナンス部品バッテリーの種類
- 総括:スーパーカブ50 カスタムパーツ
オフロード仕様にするカスタム
スーパーカブ50は、その軽量な車体とタフなエンジン、シンプルな構造から、意外にもオフロード走行の素質を秘めています。「ハンターカブ」のような本格的なオフローダーとは異なりますが、パーツの選択次第で林道ツーリングなどを楽しめる仕様にカスタムすることが可能です。
このスタイルの基本となるのは、まずタイヤの交換です。舗装路(オンロード)向けの純正タイヤから、凹凸の大きなトレッドパターンを持つ「ブロックタイヤ」に交換します。これにより、土や砂利道でのグリップ力が格段に向上し、見た目も一気にアグレッシブな雰囲気になります。タイヤにはオフロード走行の比重が高いものから、舗装路での快適性も両立させたデュアルパーパスタイプまで様々な種類があります。
次に重要なのがマフラーです。純正のようなダウンマフラーでは、路面の凹凸や障害物にマフラー本体をヒットさせてしまう危険があります。そのため、エキゾーストパイプがエンジンの上部や側面を通り、サイレンサーが高い位置に配置される「アップタイプマフラー」への交換が推奨されます。
さらに本格的に仕上げるためには、いくつかのパーツ追加が効果的です。フロントフェンダーを、タイヤとの隙間が少ない純正位置から、フロントフォークのアンダーブラケット付近に移動させる「アップフェンダー」化は、オフロードスタイルの定番です。これにより、タイヤに泥が詰まるのを防ぐ効果があります。また、未舗装路の連続する衝撃を吸収するために、純正よりもストロークが長く、減衰力の高い強化サスペンション(特にリアショック)への交換も乗り心地と走破性の向上に寄与します。
エンジン下部を飛び石や岩から守る「アンダーガード(スキッドプレート)」の装着も、エンジンケースの破損を防ぐために有効です。操作性に関しては、純正の一体型ハンドルから、好みの高さや幅を選べる「バーハンドル」に変更するカスタムも効果的です。これにより、スタンディング(立ち乗り)走行がしやすいライディングポジションを確保できますが、ハンドル交換に伴い、各種ケーブル類(アクセル、ブレーキ)や配線の延長が必要になる場合が多いです。
角目モデルのカスタムポイント

スーパーカブ50のラインナップには、伝統的な丸いヘッドライトのスタンダードモデルとは別に、1980年代後半から2000年代のキャブレター車を中心に、「カスタム」というグレード名で販売されていた「角目」ヘッドライトのモデルが存在します。この角目モデルは、一見するとビジネスバイク然とした外観ですが、実はカスタムベースとして非常に優れた資質を持っています。
最大のメリットは、トランスミッションです。当時の丸目スタンダードモデルの多くが3速ミッション(自動遠心クラッチ)であったのに対し、角目モデルは標準で4速ミッションを搭載している車両が多い点です。ギアが1速増えることで、よりエンジンパワーを有効に使えるようになり、変速ショックが少なくスムーズな走行が可能です。これはボアアップなどでパワーを上げた際にも大きなアドバンテージとなります。
第二に、セルスターターが標準装備されているモデルがほとんどであることです。キック始動の手間がなく、日常の利便性が高いことはもちろん、ボアアップなどで圧縮比が上がったエンジンでも始動が容易になります。
第三のメリットは、ハンドル径です。丸目モデルのハンドル径が19mmという特殊なサイズなのに対し、角目モデルは一般的なバイクと同じ22.2mm(7/8インチ)径を採用しています。これにより、社外品のグリップ、ブレーキレバー、スイッチボックス、ミラホルダーなど、膨大な種類のカスタムパーツがそのまま使用可能となり、バーハンドル化などを行う際のハードルが格段に低いのです。
第四に、リアフェンダーの構造が挙げられます。丸目モデルのリアフェンダーはフレームと一体の鉄製ですが、角目モデルはリアフェンダーの後部(テールランプが付いている部分)がプラスチック製の別パーツとなっており、ボルトで簡単に取り外しが可能です。これにより、鉄板を切断する大掛かりな作業(フェンダーカット)を行うことなく、リア周りをスッキリとさせた「チョップドフェンダー」スタイルを簡単に実現できます。
これらの特徴から、角目モデルは外観の好みさえ合えば、特にエンジンチューニングやハンドル周りのカスタムを考えている場合に、非常に合理的かつ優れたベース車両であると言えます。
プロカスタムの活用法とパーツ

「スーパーカブ50プロ」は、その名の通り、新聞配達や郵便配達、出前などの過酷な業務(プロユース)に耐えうるよう設計された、高耐久・高積載モデルです。一目でわかる特徴として、ハンドル前に鎮座する大型のフロントバスケット(前カゴ)と、純正スタンダードモデルよりも大幅に延長された大型のリアキャリアが挙げられます。
この圧倒的な積載能力は、ビジネスユースだけでなく、趣味の世界でも大きなメリットとなります。「プロ」モデルのこの特徴を最大限に活かし、長距離ツーリング仕様や、多くの道具を必要とするキャンプツーリング仕様のベース車両として活用するオーナーが少なくありません。大きな荷物を積んでもふらつきにくいよう、車体バランスが考慮されており、実用性を最優先するカスタムベースとして最適です。
また、現行のFIモデル(AA07など)では、スタンダードモデルの17インチとは異なる前後14インチの小径ホイールが採用されています。これは積載時の安定性や小回り性能を重視した設計ですが、この14インチホイールが生み出す無骨でタフなスタイルそのものを活かし、個性的なストリートカスタムの素材として注目する向きもあります。
プロモデルのカスタムの方向性としては、専用の大型キャリアやバスケットの利便性を活かしつつ、快適性や安全性を向上させるパーツが人気です。例えば、長距離走行の疲労を軽減するためにシートをクッション性の高いものに変更したり、夜間や悪天候時の視認性を高めるフォグランプを追加したりすることが挙げられます。また、冬場の快適性を劇的に改善する「グリップヒーター」や、走行風を強力に防ぐ大型の「ウインドシールド(風防)」、手元を寒さから守る「ハンドルカバー」なども、実用性を重視するプロモデルのカスタムと非常に相性が良いと言えるでしょう。
メンテナンス部品バッテリーの種類
様々なカスタムパーツに目を奪われがちですが、どのようなカスタムを施すにしても、まずは車両本体が健康な状態であることが大前提です。特にバッテリーは、スーパーカブの心臓部とも言える重要なメンテナンス部品です。
年式の古いキック始動のみのキャブレター車であれば、バッテリーが弱っていてもエンジン始動は可能でしたが、セルスターター付きのモデルや、電子制御燃料噴射(FI)を採用している近年のモデル(2007年以降)にとって、バッテリーは生命線です。FIモデルはバッテリーが完全に上がってしまうと、燃料ポンプが作動せず、キックでもエンジン始動ができなくなってしまいます。
バッテリー交換の目安としては、セルの回りが以前より弱々しくなった、ヘッドライトがアイドリング時に暗くなる、ウィンカーの点滅が不安定になる、といったサインが現れた時です。一般的にバッテリーの寿命は2~3年程度と言われていますが、走行頻度や環境によって前後します。
スーパーカブ50は、製造された年式やモデル(型式)によって、搭載されているバッテリーの型番(規格)が異なります。購入する際は、必ず自分の車両に適合したバッテリーを選ぶ必要があります。
スーパーカブ50 主なモデル別 適合バッテリー(参考)
| 車両モデル(主な型式) | 主な年式 | 始動方式 | 適合バッテリー型番(規格) | 特徴 |
| スーパーカブ50(C50) | 1990年代~ (12V) | キック / セル | YT4L-BS | 12Vキャブレター車のスタンダード。 |
| スーパーカブ50(AA01) | 1999年~2007年頃 | キック / セル | YT4L-BS | C50後継のキャブレター車。 |
| スーパーカブ50(AA04) | 2012年~2017年 | セル / キック | YTX4L-BS | FIモデル。YT4L-BSより高性能。 |
| スーパーカブ50(AA09) | 2017年~ | セル / キック | GTZ4V | 現行FIモデル。小型・高性能化。 |
※上記はあくまで代表的な参考例です。同じ型式でも製造時期や仕様によって異なる場合があります。交換の際は、必ず現車に搭載されているバッテリーの型番を目視で確認するか、バイクショップにて適合確認を行ってください。
近年では、純正採用されている従来の鉛バッテリーのほか、自己放電が少なく軽量な「リチウムイオンバッテリー」なども社外品として流通しています。これらは高性能ですが、価格が比較的高価であることや、専用の充電器が必要となる場合がある点に注意が必要です。
総括:スーパーカブ50 カスタムパーツ
スーパーカブ50のカスタムパーツに関する要点を以下にまとめます。
- スーパーカブ50は社外パーツが非常に豊富
- カスタムの第一歩としてマフラーやシート交換が人気
- マフラー交換は音と見た目の変化が大きい
- マフラー選びではJMCA認証など公道走行の可否を確認
- シート交換はデザイン性と機能性(足つき・疲労軽減)が目的
- レッグシールドの交換は手軽に車体の印象を変えられる
- 社外品のレッグシールドは取り付け精度に注意が必要
- ホイールカスタムはアルミリム化や太リム化が主流
- オフロードカスタムはブロックタイヤやアップマフラーが基本
- 角目モデル(カスタム)は4速ミッション搭載でカスタムベースに適している
- 角目モデルはハンドル径が22.2mmでバーハン化が容易
- プロモデルは大型キャリアを活かした積載性カスタムが人気
- カスタムの前にバッテリーなど消耗品のメンテナンスが大切
- バッテリーは年式やモデルによって適合型番が異なる
- 自分の車両に適合するパーツかしっかり確認してから購入する
